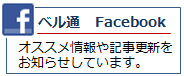スタッフY(以下Y):大学で建築を学び、それから広告代理店に就職なさったとのことですが、異業界と思われるところからファッション業界への転身した理由は何ですか?
いづみさん(以下I):そもそも“デザイン”とか“創る”ことが好きだったのですが、建築関連の場合、作品を作れるようになるまで10年、20年単位で時間がかかるので、もう少しアイデアをどんどん出せるところ、回転が速くモノづくりをできる所に行きたかったんです。
広告代理店のお仕事ではグッズやインテリアデザイン、CMタレントの衣装に関する仕事に携わりたいと思って入社して、しばらくはコピーライターの仕事をして。仕事は充実していたのですが、洋服を作りたいという気持ちが消えなくて、留学を決意しました。
Y:ファッション学校がいろいろある中でアントワープを選んだ理由は何ですか?
I:ロンドンにある「セントラル・セントマーチンズ」もファッションで有名な学校なのですが、やっぱり世界一はアントワープだと思ったので、アントワープを選びました。
Y:好きなデザイナーさんはいらっしゃいますか?
I:ドリス・ヴァン・ノッテンとマルニです。フェミニンでエレガントなデザインが好きです。
ちなみに、今日のワンピースもドリスなんです。
Y:海外でファッションを学ぶ上で御苦労なさったことはありますか?
I:イメージを英語で伝えることが一番難しかったです。例えば「文学」といったような目に見えないものを言葉で表現するのはすごく難しいし、理解されにくいし、解釈も変わってしまうんです。
あとは…最初の2年くらいは、自分のイメージと実際にできあがる服とにどうしても差ができてしまって、先生や同級生の意見に左右されすぎたり、精神的に苦労しました。課題も多くて徹夜続きだったこともありますし、体力的にもハードでした。
3年生4年生となるに従って、自分のやりたいデザインが確立されてくるので、私個人の作業という意味では楽になってくるのですが、逆にプリントやニットを業者に頼んだり、撮影をオーガナイズしたり、という共同作業が大変になってきます。
Y:デザインはどうやって生まれるのですか?
I:様々なものからインスピレーションを受けて、それらをミックスしていきます。例えば私が3年生の時の作品では、ウズベキスタンの民族衣装に50年代のクチュールをミックスしました。4年生の作品では「キース・ヴァン・ドンゲン」という、陰影の強い絵やデフォルメした女性の肖像画を描くオランダの画家からインスピレーションを受けています。
卒業コレクションのテーマは「Private Painting」で、マティスやキース・ヴァン・ドンゲンといった画家たちが描いた妻の絵をイメージしています。画家というクレイジーな人を夫に持ち、その夫と現実世界との狭間にいる「画家の妻」という立場を表現したかったんです。
Y:作品を作ってから「やっぱり違う!」と作り直したり、ボツになったりすることもあるんですか?
I:通常はデザイン画でイメージを固めてから作品の制作に入るので、完全に出来上がった後でイメージが違って作り直すということはあまりないのです。卒業コレクションの中には光と影を表現するのに2色の布を使ったドレスがあるのですが、2色だけで陰影を表現するのが難しくて。
ドールに着せたときにはきちんと陰影に見えていたはずなのに、モデルに実際に着せてみるとちょっと違う。そういう場合には、できあがってからでも作り直します。
   ※写真は2010年の卒業制作 および Van Hongo 2011年春夏コレクションです。 |
I:ちなみに、このニット(写真右、中央)は光と影を表現するために、3種類の色の違う毛糸でそれぞれレース編みをして形を作り、それらを重ねて作っているんです。
他にも、大体コートを作るのに必要なピースは10ピース程度なのですが、40ピースのパターンから作られたコートもあります。
Y:さすが、デザイナー魂。凝ってますね~。
| Y:ところで、2010年にSACHA(※)のシュー・アワードを受賞なさった靴も素敵でしたね。 I:これは、靴を履いていても裸足に見えるようなカッティングで素材も油絵で仕上げた ような質感になっています。 |
|
 |
SACHAのシュー・アワードで商品化される靴は通常100足程度なのですが、これは600足作られたんです。それでも37サイズはすぐに完売したそうです。 スタッフ一同:(驚!!) |
Y:2011年の春夏シーズンから開始する、Van Hongo について詳しく教えてください。 あとは帽子やストッキングなどのアクセサリーも作っています。 |
 |
夢を追って、あきらめずにやり遂げるだけの強い意志と精神力。 Van Hongo オフィシャルサイト (※)SACHA:オランダのシューズセレクトショップ。
|
| << 前のインタビューへ | 次のインタビューへ >> |