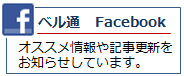|
| 第6回:ファミリーミーティングのすすめ ~アドラー心理学より~ |
 私が子育てをしていく中で、よりどころの1つにしたのが「アドラー心理学」です。 私が子育てをしていく中で、よりどころの1つにしたのが「アドラー心理学」です。 大学教授からアドラー心理学を学ぶ中で勧められたのが「ファミリーミーティング(家族会議)をすること」でした。 家族というのは、最小単位の社会であり、その中で親は、子どもが「正しい問題解決の方法」や「共同体感覚」を身につけていくサポートをする、という社会生活実践の場です。 小難しい話は後回しにするとして、7年以上続いている我が家のファミリーミーティングの流れを紹介します。 通常は日曜日の夕食後に行っています。 前日、または当日に「ファミリーミーティングする?テーマは何にする?」と声をかけ合って開催を決定します。 いつものテーマは ・今週、印象に残ったこと ・来週、楽しみなこと ・何か大きなイベント(旅行など)があったらそのことについて などです。 夕食後、食器を下げて、全員着席して「今からファミリーミーティングを始めます。お願いします。(頭を下げる)」が始まりの合図。 テーマについて一人ずつ、丁寧な言葉で話します。だれか一人が記録をとります。 話す人以外は口をはさまずに聞きます。 全員話したら、質問したり、来週の予定をそれぞれ確認して、「これでファミリーミーティングを終わります。(頭を下げる)」で終了です。 時間にして5分くらいです。 ファミリーミーティングを取り入れ始めた時、娘は2歳半でした。きちんとした意見や感想を言えない時もありましたが、ミーティングの間、席に着いていられることだけでも素晴らしいことでした。その頃の記録を読み返してみると、娘の発言は微笑ましいものがたくさんあり、成長の記録にもなっています。 また、各自の話を聞いていると、家族で同じ体験をしていても、個人によって印象に残っている場面が違っていて、そんな風に思っていたんだとか、印象に残ったのはそこ?など、家族でもそれぞれ考え方も感じ方も違うということにあらためて気づきます。 娘の通う学校の様子を見ていると、特に低学年のうちは、人が話しているときは黙って耳を傾ける、という習慣があまりないように思います。自分の意見を自由に発言できる環境も素敵ですが、このファミリーミーティングは、話す順番を守り、人の意見をきちんと聞き、自分の意見も丁寧に述べるという経験をさせてくれます。 さて、このファミリーミーティングを開催するにあたって、いくつかの留意点があります。まず、ファミリーミーティングを家族の時間に取り入れることを、家族全員が了承していることが大前提です。思春期のお子さんがいる家庭では、抵抗があるかもしれません。まずは数回やってみようなど、柔軟な姿勢で提案してみてください。 ミーティングのテーマも全員の了解で決めます。次のミーティングでテーマにしたいことを書き込むホワイトボードなどがあると思春期のお子さんでも積極的に参加できそうです。 テーマは、個人を責めたり誰かに罰を与えるようなものは避けます。 ファミリーミーティングは、アドラー心理学でいう「共同体感覚を身につけ、勇気づけ(られ)る場」なので、お子さんが小さいうちは、毎週、「楽しかったことは何?」でいいそうです。 他のテーマでもポジティブなものを選ぶといいそうです。 毎回の参加も強要はできません。気分や体調で参加したくない日があるでしょう。家族の人数によって、誰かが参加しなくても開催してもいいし、しなくてもOKです。参加しなかった人には、記録を後で見せることもお忘れなく。 各自が話したことを批判しないようにしましょう。それは違う、と意見の押し付けもしないようにしましょう。 もし、何か解決や改善が必要なことが出てきたら、こんな視点で考えてみましょう。 ・それが解決することは家族にとってどのくらい大切か。 ・そのことに関して、各自が協力できることは何か、できないことは何か。 ・そのことを解決するためにどんなルールや方法が必要か。 海外生活では、家族の協力で乗り越えていく場面が多々ありますよね。日ごろから、お互いを理解できていること、家族で話し合いができる基盤があることは、心強いものだと思います。ファミリーミーティングを「家族が一か所に集まってお互いをよく知り、絆を深める場」ととらえて、習慣として取り入れてみてはいかがでしょうか? (最近は、アドラー心理学がマンガで学べる書籍も発刊されていますので、興味のある方は気軽に 読んでみてはいかがでしょうか。)
|
| 布施智美: 大学卒業後、教職を9年間務め、夫の海外赴任に付随しアメリカへ。 コーチングを学び「(一財)生涯学習開発財団 認定コーチ」を取得しコーチングセッションを継続中。アメリカ在住時に大学教授よりアドラー心理学を学ぶ。 帰国後、厚生労働省認定CDA(キャリアディペロップメントアドバイザー)資格を取得し、就活者や転職者へのキャリアカウンセリングを行う。人がよりよく生きるサポートをすることをライフワークとするベルギー在住主婦。 |