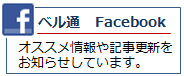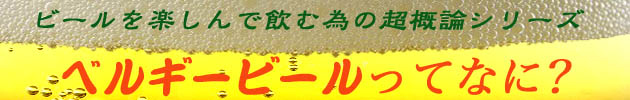 |
| No.4 ベルギービールの奥義:トラピストビール |
お待たせしました。いよいよベルギービールの奥義「トラピストビール」について解説しましょう。 |
 |
・「トラピスト」という名称は? まず知っておいていただきたいのは、「トラピストビール」という呼称の使用が許されている修道院醸造所は、世界に7ヶ所(2011年3月現在、ベルギー内に6ヶ所とオランダに1ヶ所)しかないということです。 ビールの銘柄名でいうと以下の7つ(以下、アルファベット順) Achel, Chimay, Orval, Rochefort, La Trappe, Westmalle, Westvleteren La Trappeはオランダにあるとは言え、Achelからも近い、ベルギーとの国境からすぐのところです。この7つ以外はすべてアベイビールといういう呼称しか使うことができません。このアベイビールという呼称にも決まりがありますが、説明は次回にまわしましょう。 トラピストビールを調べてみると、『トラピスト会』あるいは『シトー派』の修道院が造るビールのこと等と書かれています。「シトー」を英語かフランス語で探そうと思っても、うまく見つからないのは、カタカナ表記とは程遠いスペリングだからで、厳密にはOudo Cisterciensis、英語ではCistercian、仏語では Cistercienと綴ります。ごく単純に解説すれば、『トラピストビール』という名称は、シトー派の14の修道院によって構成される国際トラピスト協会が定めた条件を満たす場合のみ使用することができるのです。(http://www.trappist.be/) その条件とは、①カトリックの中でも戒律の厳しいベネディクト会の中から、さらに労働と祈りを重視したトラピスト会(別名、厳律シトー会)の修道院の敷地内(あるいは隣接)醸造所で造られ、②醸造所の経営が修道院の管理下にあり、③ビールの収益が地域社会とその慈善事業などに還元されること。つまり、我々がビールを飲むために支払った代金の一部が、地域の慈善事業などに寄付されているわけで、純然たる営利醸造所ではないのです。また、トラピストビールは、修道士だけによって造られていると思うのも間違い。修道院はビール造りやチーズ作りなどを通して、人々に職を提供し、地域社会に貢献してきたわけです。 そもそもなぜ戒律厳しき修道院がビール造りに携わったのでしょう。それは、6世紀、聖ベネディクトが、祈りと労働を重んじた共同生活を提唱して修道院ができたことに由来します。綱紀粛正を繰り返すうちに、トラピスト会、シトー会、さらには厳律シトー会というように、労働を重視する会派が出現し、自給自足生活の中で、地元の農産物をベースとして保存の効く飲料(醸造酒)が造られます。日本人はどうも「アルコール=後ろめたい」というイメージが強いようで、修道院がビールを造るということに違和感を覚える方が多いようですが、キリスト教では、ワインはキリストの聖血。煮沸・発酵させて保存の効くワインやビールは、中世に蔓延したおそろしい伝染病を媒介しない、命の水として尊ばれたのです。 ・トラピストビール、7つの銘柄 ベルギービールの分類でよくわからなくなるのは、原料(例:小麦→白ビール)や醸造法(例:天然酵母を使った自然発酵→ランビック)に基づくカテゴリーもあれば、トラピストのように「名称の使用制限」から来ているものなどがあり、その結果いくつものカテゴリーにまたがるビールもありえるからなのです。 トラピストがなぜベルギービールの真髄と言えるかというと、名前の由来はさておき、ユニークで味わい深いものが多く、世界のビール好きをうならせているからです。ビール好きの方には、ぜひベルギー内6ヶ所(オランダのラ・トラップまで足を伸ばして7ヶ所)の巡礼をお奨めしますが、どこも隣国との国境近くという遠く辺鄙なところにあるので、車を調達し、十分な時間をとらないと難しいでしょう。 それでは、場所的に近いところを順番に紹介していきます。 南部ワロン地域(フランス語圏) 修道院名:Abbaye Notre-Dame de Scourmont(スクールモン修道院) ブリュッセルからまっすぐ南下すること120km、フランス国境間近の人里離れた森の中にある修道院の歴史は古く、ビール造りはすでに中世から行われていたとされています。トラピスト会派の修道院となって醸造が始まったのは1862年から。トラピストビールの中で、最も早く海外に輸出され、ベルギービールを世界に知らしめる牽引車となってきました。Westmalleと並んで、技術革新・設備投資にも積極的で世界中で広く拡販されています。 シメイビールは、院内と近隣消費用のDorée(金ラベル)以外に、赤、青、白ラベルで識別され、ベルギー全国はもちろん、世界的にもよく流通されています。 Chimay Rouge (シメイ・ルージュ) 修道院名はAbbaye Notre-Dame de Saint-Remy 聖レミ聖母修道院 ブリュッセルから高速E411を南東へまっしぐらに120km、アルデンヌの景勝地・観光地の脇に、聖レミ修道院はひっそりと隠れるようにたっています。初めの修道院ができたのは1230年に遡り、中世にはすでに醸造が行われていたようですが、はっきりした醸造の記録があるのは1899年。多くの戦乱、宗教改革やフランス革命などに巻き込まれて何度も破壊、疎開を繰り返し、醸造がまともに再開したのは1952年になってからのこと。今日では地域の人々の手を借りて醸造されていますが、修道院内での消費を第一の目的として作られるので、醸造量は今も限られています。 近年では設備投資もされ、プレス関係者などにも多少は門戸を開くようになっていますが、それでも、一般見学は不可。醸造所前の駐車場には、「ここは祈るところです。静寂に」の看板が見られます。2010年大晦日の火災で、修道院はかなりの被害を蒙りましたが、醸造所は無事で醸造が続けられています。 Rochefort 6 (ロシュフォール6 ) 修道院名:Abbaye Notre-Dame d'Orval オルヴァル聖母修道院 ロッシュフォールを超えてさらに高速E411をルクセンブルグ方向へ南下し、森林の中を潜り抜けるようにして、フランスとルクセンブルグの国境近くまで走ると、左手にクリーム色の石造りの壮麗な修道院が忽然と現れます。それが、オルヴァルのノートルダム修道院です。 修道院の歴史は11世紀まで遡ります。長い歴史の中で、何度も、災害や戦争による、略奪、破壊、荒廃を繰り返しますが、かなり初期の頃から、ビール醸造が行われていたという記録が残っています。1786年のフランス革命時には、ベルギーの多くの修道院や教会と同様に略奪され、焼失してしまいます。その後、再興されたのは、1926年になってから。再建の費用を捻出する手段として、1931年に醸造所が建てられ、ドイツ人醸造技術者によってオルヴァルビールが造られたのです。 オルヴァルビールは、現存するトラピストビールの中でも極めてユニーク。他では、アルコール度数や色味の異なる何品目かのビールを醸造しているのに対し、オルヴァルはたった一品目。2種類の酵母菌を3回に分けて投入したり、英国流の「ドライ・ホッピング」(熟成タンクに、大袋に入れた乾燥ホップの花をふんだんに漬け込む)という手法を用いたり、また醸造から熟成まで神秘の15℃を保つなどの方法によって、他に類を見ない複雑で香り豊かな琥珀色のビールを作り上げています。また、個性的なピン型の瓶も、聖杯型のグラスも、生まれた当時からほとんどそのままの姿で踏襲されている一方、近年は大規模な設備投資が行われ、醸造・熟成設備が一新されました。トラピストの最高峰とも言われる所以です。 現在の修道院の横には、12世紀以来度々破壊されては立て直された修道院跡の遺跡が一般に公開されており、修道院での生活を紹介するビデオも上映されています。また、修道院前のAnge Gardien (アンジュ・ガルディアン、守護の天使)というカフェでは、オルヴァルチーズを使った軽食とともに、修道院内消費用のグリーンラベルも体験できます。 Orval(オルヴァル) 北部フランダース地域(オランダ語圏) 修道院名:Sint-Sixtusabdij van Westvleteren(聖シクステュス修道院) 北海沿岸に近いので、海辺の街De Panneやデルヴォー美術館のあるSt.Idesbaldなどと供に、ミニ・ヴァカンスを計画すとよいかもしれません。まず、http://www.sintsixtus.be/eng/brouwerijactueel.htmで、販売日とビールの種類をチェックし、070/21 00 45に根気良く電話して予約してから出かけます。修道院前のレストランカフェIn de Vredeは改装され、雰囲気も食べ物もまずまず。中には、トラピスト修道院での生活を解説するClaustrumというミニ・ミュージアムもあります。 http://www.indevrede.be/ Westvleteren Blond(緑キャップ) ⑤Westmalle (ウェストマール) 修道院名はABDIJ DER TRAPPISTEN VAN WESTMALLE アントワープから北東30キロあまり離れた、広々とした平原の森の中に12世紀以来存在してきた修道院は、醸造開始がトラピスト中最も古く1836年に院内での飲み物として醸造を始めたとされています。商業用販売を決めた1921年以降拡充を続け、技術的にも設備的にももっとも精力的で大規模な修道院醸造所のひとつです。 Westmalleでは、修道院内消費用のエキストラ(3.5%)は別とすると、ダブルとトリプルという2種類のビールを上市していますが、アルコール度数が高い黄金色の上面発酵ビールを成功させ、多くの追従を招いたのがトリプル。世界のビール醸造家や評論家から「死ぬ前に飲みたいもう一本」とされるビール通のビールとして定評があります。 国道12号線沿いの修道院に入る道の反対側にはCafé Trappistenという立派なカフェがあり、通常流通していないエキストラも味わえます。地元のおじちゃんおばちゃんに交じって多数の外国人のベルギービール巡礼者がビールを楽しむ光景を目にすることができます。 http://www.trappisten.be/ Westmalle Double (ウェストマール・ダブル) 修道院名は、Sint-Benedictus Abdij(聖ベネディクト修道院) 最初にビール醸造を始めたのは19世紀とされていますが、大戦中はドイツ兵の占領略奪などにより何度も醸造が中断されました。Westmalle, Orval, Rochefortなど醸造経験豊かなトラピスト修道院の協力を得て1998年に再スタート。 Achel 5 修道院名:abdij O.L.V. van Koningshoeven (コーニングショーヴェン聖母修道院) Achelからオランダに入り50km余り北上したところに、ラ・トラップ修道院があります。厳密に言えば、「ベルギービール」ではありませんが、世界で7つしかないトラピストビールなので、簡単に紹介しておきましょう。 ここに最初に修道院ができたのは19世紀後半と比較的新しく、資金源として早々に醸造を始めました。ラ・トラップ修道院のビールがベルギー内の他のトラピストビールを異なるのは、当初は下面発酵のラガービールでスタートしたこと、今日に至るまで、何度も民間の醸造所への委託生産を行ったため、何度かにわたって「トラピストビール」の呼称が使用できない時期があったことなどです。もっとも最近では、2005年に大規模な設備投資を行い、改めてラ・トラップ修道院内醸造所だけで醸造することになったことから、トラピストの名称を冠することが許されるようになり、今日では世界中に輸出されています。 La Trappe Blond(ラ・トラップ・ブロンド) 【最新情報】トラピストビール人気につけこんで、世界中あちこちのトラピスト修道院で資金稼ぎのビール造りが噂される中、2011年前半に8つ目のトラピストビール登場として話題になったMont des Cats(フランス国境側のトラピスト醸造所が発売)は、実は、在ベルギーのトラピスト醸造所のChimayで造られるもの。醸造所自体がこのフランスのトラピスト修道院内にないので、厳密な意味では8つ目のTrappistと呼ぶことはできないのです。一方、ベルギー・オランダ国境際のZundert のMaria Toevlucht修道院が、現在敷地内に醸造所設立を計画中とのことで、うまく行けば2012年末までに8つ目のトラピストビール登場ということになると期待されています。(2011年11月時点) |
| 著者:栗田路子(くりた みちこ) 神奈川県生まれ。上智大学卒業後、外資系広告代理店勤務。米国コーネル大学およびベルギー・ルーヴァン大学にてMBA(経営学修士)取得。90年代始めから、ベルギービールの日本向け輸出・マーケティングに従事してきたが、2007年4月、セミ・リタイヤ宣言。現在は、寄稿や執筆、日本のメディアのためのリサーチやコーディネートなどを請け負っている。ベルギービールの他、教育、医療、障害児など、守備範囲は広い。 ベルギー在住。2010年にベルギービール騎士の会の「名誉騎士」に任命される。 夫とともに㈱マルチライン経営の他、コーディネータースクラブ・ベルギーを運営。障害孤児の養子縁組を支援するチャリティ「ネロとパトラッシュ基金」運営。 障害を持つ子供と供に赴任する日本人駐在員をサポートする「元気ママの会」主催。 今までの寄稿をアップしたブログはこちらから。 |
ホームへ | 「ベルギービールってなに?」連載一覧へ | ビールのトップページへ